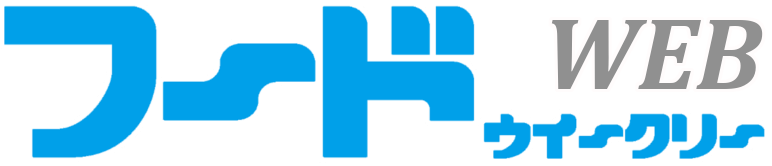コナモン百選を8品

一般社団法人日本コナモン協会(熊谷真菜会長)は10月3日、「食文化100年継承・鉄板会議」第4回全国大会を大阪・なんばのYES THEATERで開催。今年のテーマは「お好み焼の継承問題『店の継承、技の継承』」。業界関係者が課題を共有し、文化継承に向けた議論が行われた。また、「文化を味わう!コナモン100選」には、全国から8品目が選出された。

熊谷会長
第1回「お好み焼」、第2回「やきそば」、第3回「たこやき」をテーマに開催してきた鉄板会議。第4回目となる今年は「お好み焼継承問題」を取り上げ、北海道・関東・東海・大阪・兵庫・香川・愛媛・広島・福岡・宮崎の全国10カ所でエリア会議を実施した。大阪・関西万博で多くの観光客でにぎわう大阪でも、特に人気の高いメニューのお好み焼。一方、若者の間ではお好み焼離れが進み、閉業する店舗も後を絶たない。2035年までに店舗が半減する危機、「お好み焼2035年問題」が浮き彫りとなった。
全国大会では、文化功労者で食文化研究の第一人者・石毛直道氏がビデオメッセージで来賓挨拶。文化庁生活文化連携担当・長谷部勝参事官補佐が「100年フードとお好み焼の継承」についてプレゼンテーションを行った。
熊谷会長は全国100店舗で実施した、継承についてのアンケート結果を報告。後継者不在と答えたのは51店舗、原料コストの高騰を課題としたのは73店舗に上った。また、全国10カ所のエリア会議の成果も紹介。東海エリアでは、名古屋めしライターのSwind氏が愛知流お好み焼文化を解説。テイクアウト文化が根付き、二つ折りにしてアルミシートで提供する独自のスタイルが注目を浴びた。また、愛媛エリアでは、三津浜焼き推進プロジェクトを担当する二神弘樹氏が、紅白ちくわや味付けうどん・そばを用いた「三津浜焼き」を紹介。のぼりやステッカー、グルメイベントへの出店で地域名物として普及活動を進めている。
さらに、30カ国の外国人を対象に実施したお好み焼意識調査の結果も発表し、外国人から見たお好み焼文化の魅力を報告。熊谷会長は「技術と伝統があるお好み焼文化の価値を、価格に反映させることが重要」と強調した。

左からオタフクソースの大内氏、日清製粉ウェルナの目黒氏、キユーピーの猿渡氏
協賛企業のオタフクソースからはマーケティング部長の大内康隆氏が登壇し、「お好み焼店の現状と課題」をテーマに発表。同社調査による25年のシーン別の喫食頻度やお好み焼市場の動向に触れたほか、2024年1~11月の倒産件数が過去最高水準に達していることを報告。倒産の背景には、原材料コストが高騰する中でも〝1千円の壁〟を破れずにいる現状があると指摘した。同社では、お好み焼店の新規開業者に向けた支援や、広島県内で展開するお好み焼き店巡りを促進するデジタルスタンプラリーなどの取り組みを通じ、文化継承に取り組む構えを示した。スタンプラリーについては、今後、広島以外の地域にも拡大していく意欲を見せた。
日清製粉ウェルナからは商品開発部の目黒憲和氏が登壇。同社のお好み焼粉の歩みを紹介し、西日本から東日本へと普及していった軌跡や、家庭用お好み焼粉市場の動向を報告した。目黒氏は「お好み焼は経済的であり、生鮮食材との連動も可能な点から、消費者・流通双方にメリットが多い。今後も伸びしろの高いメニュー」とコメントした。
今年100周年を迎えたキユーピーからは、大阪支店長・執行役員の猿渡守氏が登壇。100年にわたるマヨネーズの歴史を振り返りながら、「コナモンとマヨネーズは切っても切り離せない関係。文化の継承に微力ながら貢献していきたい」と締めくくった。
国際的な視点では、日本コナモン協会タイ支部長の塩谷知己氏がタイのコナモン事情を報告。日本食需要が安定しており、「銀だこ」の出店や冷凍コナモンの普及も進んでいる。一方、サーモンやエビ、カニカマなどを用いたたこ焼きも登場しており、現地で独自に進化したメニューも見られた。塩谷氏は「タイでは鉄板・屋台文化が根付いており、コナモンの発展において大きなポテンシャルを秘めている」と語った。
最後に、「文化を味わう!コナモン100選」に認定された8品を発表。①「おきりこみ」(群馬県)②「焼きまんじゅう」(同)③「餃子」(栃木県宇都宮市)④「羽根つき餃子」(東京都大田区)⑤「ひとくち餃子」(大阪府大阪市)⑥「鉄なべ餃子」(福岡県)⑦「生餃子持ち帰り」(宮崎県)⑧「素焼き」(愛媛県松山市)。今年で認定は計39品目となった。
2025年10月13日付