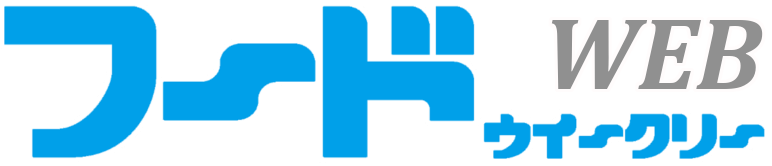大阪・関西万博が始動

熊谷会長
2025年4月13日、ついに大阪・関西万博が開幕した。国内外から多数の来場者が見込まれ、大阪の街は熱気に包まれている。そんな中、注目を集めるのが「たこ焼き」や「お好み焼き」といった鉄板粉もん文化だ。大阪の食文化として親しまれてきたが、近年は後継者不足など課題も指摘されている。大阪の食文化の魅力をどう次世代に伝えるか。40年以上にわたり粉もんの研究と普及に取り組んできた日本コナモン協会の熊谷真菜会長に話を聞いた。
お好み焼きの誕生
明治時代、西洋料理の影響を受け、ソースやキャベツを使った「洋食焼き」が現在のお好み焼きの原型とされる。当時は駄菓子として親しまれていたものが、大正から昭和にかけて各店で具材に工夫を凝らし発展していった。
戦後、広島に定着した「重ね焼き」が先に全国にあったが、具材を生地に混ぜ込む「混ぜ焼き」が主流になる。これには、花街文化が関係していると熊谷会長は推測する。甘党茶屋が洋食焼きを扱うようになり、客が「自分で焼きたい」と希望したことがきっかけで、「混ぜ焼き」が関西風として全国に広まったという。
食文化の継承と課題
熊谷会長は「〝食〟の魅力は味だけでなく、そこにある歴史や暮らしの背景にもある」と述べる。2017年には、文化芸術基本法が改正され「食文化」が正式に日本の文化として認められた。
一方で、現場では「お好み焼き2035年問題」ともいわれる課題が浮上している。近年、コスト上昇が続く中、後継者不足や採算性の低下により、個人経営の店が減少し、将来的にはお好み焼き店の数が半減する可能性があるという。特に個人店は、文化を守る役割を果たしているにもかかわらず、価格を上げづらく利益を確保しにくい状況だ。
そのためにも、文化芸術基本法に「食文化」が正式に明記されたことは大きな一歩だった。この動きを追い風に、熊谷会長は学術論文やWEBアーカイブの整備、地域店主との連携など、多角的に取り組みを進めている。
その一環として22年から始動したのが「食文化100年継承・鉄板会議」だ。これまで、お好み焼き・焼きそば・たこ焼きをテーマに全国をまわり、エリア会議で店主らと記録を集め、議論を重ねてきた。
日本の食は今や成熟期にあり、ただ美味しいだけでは差別化が難しい時代。そんな中で「何を食べるか」だけでなく、「どんな背景があるか」「誰がどのように伝えているか」が重要な視点になっている。熊谷会長は「食文化=食の物語」を正しく伝承していくことで、厳しい環境を打破できると確信している。
食文化のグローバル化
「今の時代、お好み焼きを焼くのが日本人とは限らない」と熊谷会長は話す。都内のお好み焼き店で、海外出身の焼き手たちが美味しく焼き上げていくのを見て、国内外問わず、思いのある人に継承を委ねる必要を感じたという。
万博はこうした食文化の発信の場として絶好の機会だ。熊谷会長は大阪商工会議所と連携し飲食各店での「おもてなし」を進める。たこ焼きの上にオムレツをのせた「オムレツボンバー」や「道頓堀やきそば」のPRを行い、さらにビーガン対応メニューの普及を目指す。
文化は人から人へと受け継がれるもの。大阪で生まれた粉もん文化は、国内外で新たな形に進化しながら未来へとつながっていく。関西万博をきっかけに、その魅力がさらに広がることが期待される。
2025年4月21日付